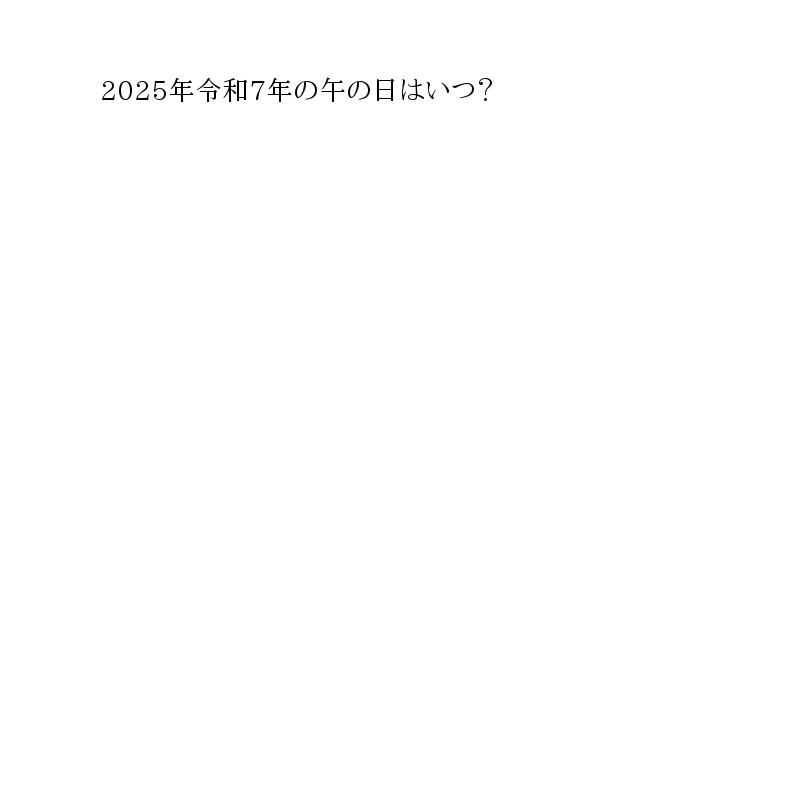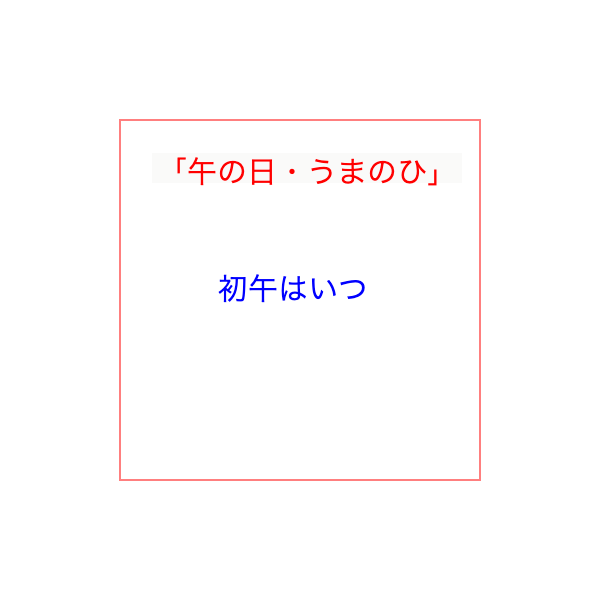「2025年・令和7年」今年の「午の日・うまのひ」初午はいつ?
「2025年・令和7年」今年の巳年(みどし)の12日に一度回ってくる午の日(うまの日 ・うまのひ)です。今年の午の日暦一覧カレンダー付き。
2025年令和7年の午の日
| 午の日 うまのひ | 日付 | 旧暦 |
|---|---|---|
| 庚午こうご(かのえうま) | 1月1日(水曜日)(先勝) | 2024年12月2日 |
| 壬午じんご(みずのえうま) | 1月13日(月曜日)(先勝) | 2024年12月14日 |
| 甲午こうご(きのえうま) | 1月25日(土曜日)(先勝) | 2024年12月26日 |
| 丙午へいご(ひのえうま) | 2月6日(木曜日)(先負) | 2025年1月9日 |
| 戊午ぼご(つちのえうま) | 2月18日(火曜日)(先負) | 2025年1月21日 |
| 庚午こうご(かのえうま) | 3月2日(日曜日)(仏滅) | 2025年2月3日 |
| 壬午じんご(みずのえうま) | 3月14日(金曜日)(仏滅) | 2025年2月15日 |
| 甲午こうご(きのえうま) | 3月26日(水曜日)(仏滅) | 2025年2月27日 |
| 丙午へいご(ひのえうま) | 4月7日(月曜日)(赤口) | 2025年3月10日 |
| 戊午ぼご(つちのえうま) | 4月19日(土曜日)(赤口) | 2025年3月22日 |
| 庚午こうご(かのえうま) | 5月1日(木曜日)(先勝) | 2025年4月4日 |
| 壬午じんご(みずのえうま) | 5月13日(火曜日)(先勝) | 2025年4月16日 |
| 甲午こうご(きのえうま) | 5月25日(日曜日)(先勝) | 2025年4月28日 |
| 丙午へいご(ひのえうま) | 6月6日(金曜日)(先負) | 2025年5月11日 |
| 戊午ぼご(つちのえうま) | 6月18日(水曜日)(先負) | 2025年5月23日 |
| 庚午こうご(かのえうま) | 6月30日(月曜日)(大安) | 2025年6月6日 |
| 壬午じんご(みずのえうま) | 7月12日(土曜日)(大安) | 2025年6月18日 |
| 甲午こうご(きのえうま) | 7月24日(木曜日)(大安) | 2025年6月30日 |
| 丙午へいご(ひのえうま) | 8月5日(火曜日)(大安) | 2025年6月12日 |
| 戊午ぼご(つちのえうま) | 8月17日(日曜日)(大安) | 2025年6月24日 |
| 庚午こうご(かのえうま) | 8月29日(金曜日)(先勝) | 2025年7月7日 |
| 壬午じんご(みずのえうま) | 9月10日(水曜日)(先勝) | 2025年7月19日 |
| 甲午こうご(きのえうま) | 9月22日(月曜日)(友引) | 2025年8月1日 |
| 丙午へいご(ひのえうま) | 10月4日(土曜日)(友引) | 2025年8月13日 |
| 戊午ぼご(つちのえうま) | 10月16日(木曜日)(友引) | 2025年8月25日 |
| 庚午こうご(かのえうま) | 10月28日(火曜日)(仏滅) | 2025年9月8日 |
| 壬午じんご(みずのえうま) | 11月9日(日曜日)(仏滅) | 2025年9月20日 |
| 甲午こうご(きのえうま) | 11月21日(金曜日)(大安) | 2025年10月2日 |
| 丙午へいご(ひのえうま) | 12月3日(水曜日)(大安) | 2025年10月14日 |
| 戊午ぼご(つちのえうま) | 12月15日(月曜日)(大安) | 2025年10月26日 |
| 庚午こうご(かのえうま) | 12月27日(土曜日)(赤口) | 2025年11月8日 |
午の日とは
「午の日」(うまのひ)十二支の午の日。干支(えと)を日に当てはめたもので7番目のうま。動物で「馬」。方角は南。月は6月、時間は11時から13時。令和7年の今年の午の日は2025年2月6日、2025年2月18日、2025年1月1日(水曜日)、2025年1月13日(月曜日)、2025年1月25日(土曜日)、2025年2月6日(木曜日)、2025年2月18日(火曜日)、2025年3月2日(日曜日)、2025年3月14日(金曜日)、2025年3月26日(水曜日)、2025年4月7日(月曜日)、2025年4月19日(土曜日)、2025年5月1日(木曜日)、2025年5月13日(火曜日)、2025年5月25日(日曜日)、2025年6月6日(金曜日)、2025年6月18日(水曜日)、2025年6月30日(月曜日)、2025年7月12日(土曜日)、2025年7月24日(木曜日)、2025年8月5日(火曜日)、2025年8月17日(日曜日)、2025年8月29日(金曜日)、2025年9月10日(水曜日)、2025年9月22日(月曜日)、2025年10月4日(土曜日)、2025年10月16日(木曜日)、2025年10月28日(火曜日)、2025年11月9日(日曜日)、2025年11月21日(金曜日)、2025年12月3日(水曜日)、2025年12月15日(月曜日)、2025年12月27日(土曜日)、の31回あります。
午の日の由来・行事・初午(はつうま)
2月の最初の「午の日」が「初午」(はつうま)で京都の伏見稲荷をはじめ、大阪の玉造稲荷、愛知県の豊川稲荷など、各地の稲荷神社で祭事が行われる。
稲がなることを意味する「いなり」から、五穀豊穣や商売繁盛、家内安全を祈願する。狐の好物が油揚げであることから、初午には、「油揚げ」や「いなり寿司」を奉納するようになった。稲荷神はキツネではなく、キツネは稲荷神の使い。
その他の初午の食べ物は初午団子(繭がたくさんとれるように「まゆ」の形をした団子を作って神様にお供えしたのが始まり)や、しもつかれ(栃木県伝わる郷土料理)、旗飴(奈良県の飴菓子)など。
2025年の「初午」の日、一の午は2月6日(木)二の午は2月18日(火)です。
2025年の子の日 2025年の丑の日 2025年の寅の日 2025年の卯の日
2025年の辰の日 2025年の巳の日 2025年の午の日 2025年の未の日
2025申の日 2025年の酉の日 2025年の戌の日 2025年の亥の日
2025年の初午まとめ
- 2025年の初午は2月6日(木)、二の午は2月18日(火)です。
初午(はつうま)とは、2月の最初の午の日にあたり、稲荷神社で「初午祭」が行われる日です。初午の由来は、京都の伏見稲荷大社に由来しており、和銅4年(711年)の2月初午の日に穀物の神様である稲荷大神が稲荷山に降り立ったとされています。
初午の日は、古来より「午」の刻、すなわち正午に太陽が天頂に達することから、最も吉兆とされてきた。この日は一年の中で運気が最高潮に達し、縁起の良い日と伝えられている。
本来であれば旧暦二月の最初の午の日が「初午」ですが、現在では新暦2月の最初の午の日としているところが多い。新暦の3月となる場合もある。
- 3月2日(日曜日)(仏滅)「旧暦で2025年2月3日(庚午こうご(かのえうま))」
- 3月14日(金曜日)(仏滅)「旧暦で2025年2月15日(壬午じんご(みずのえうま))」
- 3月26日(水曜日)(仏滅)「旧暦で2025年2月27日(甲午こうご(きのえうま))」
初午には、五穀豊穣や商売繁盛、家内安全を祈願して、各地の稲荷神社でお祭りが行われます。また、初午の行事食としては、油揚げやいなりずしなどが奉納されます。これは、稲荷神のお使いがきつねで、その好物が油揚げであることに由来しています。
初午の日には、スーパーやコンビニで稲荷ずしが販売される光景が見られます。初午の日は毎年異なり、例えば2025年は2月6日(木)、2026年は2月1日(日)です。旧暦の2月(新暦の3月)に行事を行う地域もあります。
毎年2月11日は「初午いなりの日」という記念日として制定されています。
初午祭
初午祭は、京都の伏見稲荷大社を総本宮とする全国の稲荷神社で行われるお祭りです。2月の最初の午の日に開催され、豊作や商売繁盛、開運、家内安全を祈願する行事です。
初午祭の由来は、和銅4年(711年)2月の初午の日に、稲荷大神が伏見稲荷の三ヶ峰に降臨したことにあります。初午祭が行われる主な神社には、以下のものがあります。
- 大阪の玉造稲荷
- 愛知県の豊川稲荷
- 鎌倉市の佐助稲荷神社
- 鹿児島県霧島市の鹿児島神宮
また、2月の2回目の午の日を「二の午」、3回目を「三の午」と呼び、これらの日にも祭りを行ったり、二の午もしくは三の午にのみお祭りを行う地方もあります。
初午の行事と地域の特色
初午の日には、地域ごとに独自の特色ある行事や風習が見られます。特に稲荷信仰が深い地域では、初午祭が盛大に行われます。
初午祭の際には、多くの神社で参拝者に「開運招福」や「商売繁盛」のご祈祷が行われるほか、特別な絵馬やお守りが授与されることもあります。また、屋台や地元の特産品の販売が行われ、地域の賑わいを見せる神社も少なくありません。
初午の食文化
初午の日に食べられる代表的な料理は、油揚げを使ったいなりずしです。稲荷神のお使いとされるきつねの好物が油揚げであることから、全国の稲荷神社で奉納されます。また、地域によっては甘酒や赤飯を振る舞う神社もあります。
初午の日には、以下のような食材や料理が親しまれます。
- 油揚げ: 稲荷神のお使いであるきつねに由来。
- いなりずし: 油揚げを用いた寿司。
- 甘酒: 身体を温める飲み物として人気。
- 赤飯: お祝いの日に欠かせない食べ物。
初午の日には、稲荷神社にゆかりのある伝統的な食べ物を食べる習慣があります。地域ごとに特色ある食文化が発展しており、初午の祈願や行事に欠かせない料理が楽しめます。以下に代表的な料理をご紹介します。
いなり寿司
いなり寿司は、稲荷神社の神様である稲荷大神のお使いとされる狐の好物、油揚げを使った定番料理です。いなり寿司は稲荷神社に供えられるほか、家庭でも広く親しまれています。
- 東日本: 米俵に見立てた俵型が一般的です。
- 西日本: 狐の耳をイメージした三角形の形が多く見られます。
初午団子
初午団子は、富山県の郷土料理で、白い繭のような形をした団子です。養蚕が盛んだった富山県では、初午の日に蚕の神様を祀る行事があり、繭がたくさんできることを祈願して、この団子が作られるようになったと伝えられています。
しもつかれ
しもつかれは栃木県の郷土料理で、初午の日に欠かせない一品です。鮭の頭、大根の鬼おろし、にんじん、油揚げ、節分の残り豆を酒粕と一緒に煮込んで作ります。この料理には、稲荷神社に供える風習があります。
- 稲荷神社へのお供え: 藁を束ねて作った「わらづと」にしもつかれを入れ、赤飯と一緒に奉納します。
- 初午の日の意味: 五穀豊穣や家内安全を祈願し、地域の伝統を感じる料理として親しまれています。
初午の日には、いなり寿司や初午団子、しもつかれなどを味わいながら、古くから伝わる日本の伝統文化を楽しむことができます。地域特有の料理を取り入れることで、初午の日の意味を深く感じることができるでしょう。
初午の記念日「初午いなりの日」
毎年2月11日は「初午いなりの日」として制定されています。この日は、稲荷神社への参拝やいなりずしを食べることで、豊作や商売繁盛を祈願することが奨励されています。スーパーやコンビニでは、初午に合わせて特設コーナーが設置され、いなりずしが多く並びます。
初午の「正一位」意味とは?
初午祭では、「正一位稲荷大明神」と記された幟旗が掲げられ、油揚げや赤飯が供えられます。
「正一位」の由来と歴史
- (律令制下朝廷から諸臣に授けられた位階で、官人の地位を表す等級として一位から初位の位階がありました。
- 「正一位」は神様の最高位で、天長4年(827年)に「従五位下」を授かり、天慶5年(942年)に「正一位」となりました。
- 奈良時代中期以降、この位階が人に対してでなく、神にも授位されるようになりました
- 伏見稲荷大社を「狐の本所」とする観念と関わりながら「狐の官位」として普及していきました
(「正一位」の神様は他にもたくさんおられます。)
初午祭を楽しむポイント
初午祭をさらに楽しむためのポイントとして、以下を参考にしてください。
- 近隣の稲荷神社を訪れ、参拝をして五穀豊穣や家内安全を祈願。
- 家庭でいなりずしを作り、家族で初午を祝う。
- 地域の初午祭に参加し、地元の伝統文化を体験。
初午の日は、稲荷信仰に基づく日本の伝統的な文化を感じられる貴重な機会です。家族や友人と共に、その歴史や意味を楽しんでみてはいかがでしょうか。