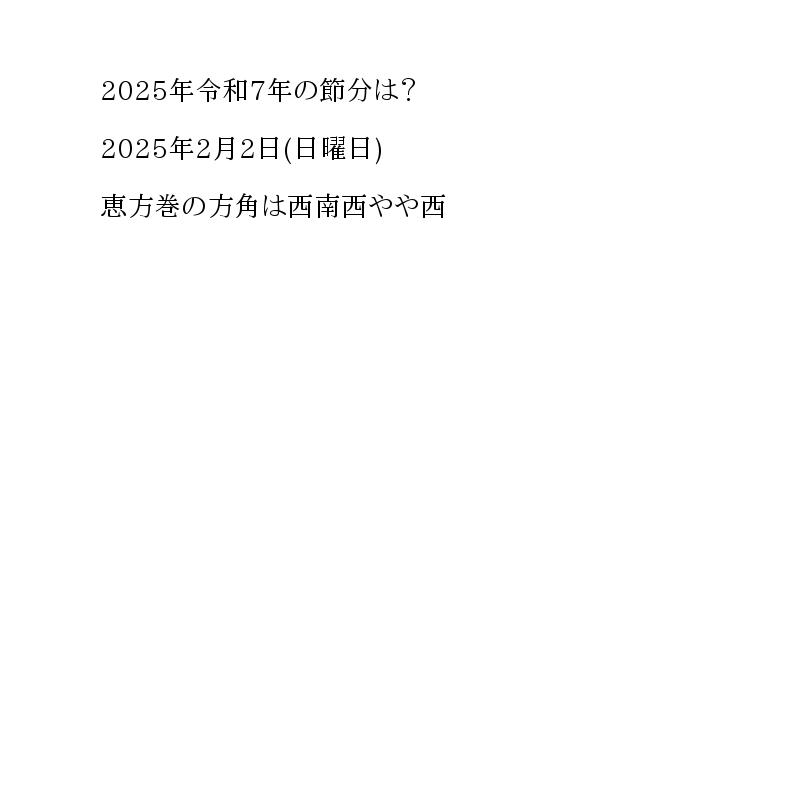「2025年・令和7年」今年の恵方巻きの方角・節分はいつ?
「2025年・令和7年」今年の巳年(みどし)の節分です。今年の節分カレンダー付き。
「2025年・令和7年」今年の節分
| 行事 | 日付 | 恵方の方角 |
|---|---|---|
| 節分 | 2025年2月2日(日曜日) | 西南西やや西 (時計回りに255度) |
- 節分とは
- 節分の由来
- 節分の豆まき
- 節分の食べ物
- 2025年の恵方の方角は?
- 2025年令和7年の節分は何日前?
- 2025年の節分カレンダー
- 節分 2025・2026・2027年の一覧表
- 節分2025年過去一覧
- 節分2025年恵方参り・方角の地図
- 節分2025年まとめ
節分とは
「節分」(せつぶん)。立春の前日。邪気を払い無病息災を願う行事。豆まきをする日。
令和7年の今年の節分は2025年2月2日(日曜日)壬寅(大安)です。
節分の由来
中国から伝わった「追儺」(ついな)(大晦日や節分など季節の変わり目に邪気(鬼)が生じると信じられていたため追い払う行事)が平安時代頃に広まり現在の節分となった。
節分とは雑節の一つで、各季節の始まりの日(立春・立夏・立秋・立冬)の前日のこと。実際は春、夏、秋、冬と年に4回ある。
春の節分は立春の前日の2025年2月2日(日)、夏の節分は立夏の前日の2025年5月4日(日)、秋の節分は立秋の前日の2025年8月6日(水)、冬の節分は立冬の前日の2025年11月6日(木)となる。
立春が旧暦で12月の大晦日にあたり、年越しの日であるとともに一年の区切りであるため4回の節分の中で年明けの2月の節分、春の節分が残ったとされる。
2月の節分は立春の前日だが(太陽黄経が315度となる日で天体の運行に基づいているため)立春の日付は年によって異なる。(1984年は2月4日、2021年、2025年は2月2日など。)
節分の豆まき
節分の日には玄関などに焼いた鰯の頭に柊の小枝をさしたもの柊鰯(ひいらぎいわし)をおく。「お庭外、福はうち」と掛け声をかけて豆を撒く。そして自分の歳の分だけ豆を食べて厄除けを行う。そして恵方巻きを食べる。
節分の食べ物
「福豆」豆まきを終えてから食べる。自分の年齢あるいは年齢に1つ加えた数だけ食べる。
「恵方巻き」「丸かぶり寿司」七福神にちなんだ7種類の具材が入った太巻き寿司。恵方を向いて食べる。関西が発祥。
1980年代に大手コンビニエンスストアのセブンイレブンが丸かぶり寿司に目を付け、「恵方巻」として展開して全国的に広まる。
始まりの由来として明治時代に大阪・船場の旦那衆が節分の日に花街の遊女に巻きずしを丸かぶりさせ大尽遊びをしていた説がある。
恵方巻きの食べ方はお願い事をしながら、恵方を向いて、食べ終わるまで黙って、一気に食べる。地域によって細かい取り決めがあるがこの食べ方が最低限のルールとなる。
「節分いわし」西日本。鰯の焼き魚。
「福茶」福豆、梅、昆布を入れたお茶。
「厄除けぜんざい」 関西地方。厄年の人がぜんざいを振る舞う。
「鯨」 山口県。大きいものを食べると縁起が良いとされている。
「けんちん汁」 関東。鎌倉にある建長寺汁が起源の精進料理。
「こんにゃく」 四国地方。砂おろしや胃のほうきと呼ばれる。体内の掃除。
「とろろ汁」 長野県。長芋を鬼のツノに見立ててすりおろして食べる。鬼退治の意。
「節分蕎麦」 旧暦で立春前日の節分は大晦日。旧暦の年越しそば。
2025年の恵方の方角は?
「恵方」とは、その年の福徳を司る歳徳神(としとくじん、とんどさん、その年の福徳を司る神)のいる方角。「東北東」「西南西」「南南東」「北北西」の4つの方角のみでその方角に向かって事を行えば何事も吉とされている。そのため恵方巻きは恵方を向いて食べるとよいとされています。
十干と恵方の一覧表
| 十干 | 恵方 |
|---|---|
| 甲(きのえ)・己(つちのと) | 東北東やや東(75度) |
| 乙(きのと)・庚(かのえ) | 西南西やや西(255度) |
| 丙(ひのえ)・辛(かのと)・戊(つちのえ)・癸(みずのと) | 南南東やや南(165度) |
| 丁(ひのと)・壬(みずのえ) | 北北西やや北(345度) |
恵方は十干(じっかん)の方位で決められている。また西暦の下一桁、1の位が0と5の時恵方は「西南西」、西暦の1の位が1と3と6と8は「南南東」、西暦の1の位が2と7は「北北西」、西暦の1の位が4と9は「東北東」と西暦で調べることもできる。
2025年の節分の恵方は「西南西やや西」で時計回りに255度の方角です。
2025年令和7年の節分は何日前?
2025年令和7年の節分は何日?今日から日数で159日前、0年5ヶ月9日前の2025年2月2日(日曜日)です。
2025年2月の節分カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 仏滅 | ||||||
| 2 大安 | 3 赤口 | 4 先勝 | 5 友引 | 6 先負 | 7 仏滅 | 8 大安 |
| 9 赤口 | 10 先勝 | 11 友引 | 12 先負 | 13 仏滅 | 14 大安 | 15 赤口 |
| 16 先勝 | 17 友引 | 18 先負 | 19 仏滅 | 20 大安 | 21 赤口 | 22 先勝 |
| 23 友引 | 24 先負 | 25 仏滅 | 26 大安 | 27 赤口 | 28 友引 |
2025-02-11(火曜日)建国記念の日
2025-02-23(日曜日)天皇誕生日
2025-02-24(月曜日)振替休日
節分 2025・2026・2027年の一覧表
| 行事 | 日付 | 恵方 |
|---|---|---|
| 2025年の節分 | 2025年2月2日(日曜日) | 西南西やや西 |
| 2026年の節分 | 2026年2月3日(火) | 南南東やや南 |
| 2027年の節分 | 2027年2月3日(水) | 北北西やや北 |
| 2028年の節分 | 2028年2月3日(木) | 南南東やや南 |
| 2029年の節分 | 2029年2月2日(金) | 東北東やや東 |
| 2030年の節分 | 2030年2月3日(日) | 西南西やや西 |
- 2025年の節分は2025年2月2日(日曜日)恵方は西南西やや西
- 2026年は2月3日(火)南南東やや南
- 2027年は2月3日(水)北北西やや北です。
節分2025年過去一覧
| 行事 | 日付 |
|---|---|
| 2025年の節分 | 2025年2月2日(日曜日) |
| 2024年の節分 | 2024年2月3日(土) |
| 2023年の節分 | 2023年2月3日(金) |
| 2022年の節分 | 2022年2月3日(木) |
| 2021年の節分 | 2021年2月2日(火) |
| 2020年の節分 | 2020年2月3日(月) |
2025年の節分のまとめ
2025年の節分は、日本の伝統行事であり、特に家族や友人と豆まきを楽しむ日です。2025年の節分は「2月2日(日曜日)」に行われます。節分の日には、立春の前日として、邪気を払うための豆まきや恵方巻きを食べる風習があります。
2025年の節分の日に行うべきこと
- 豆まき: 「鬼は外!福は内!」と声を上げながら福を呼び込みましょう。
- 恵方巻き: 今年の恵方は「西南西やや西」。恵方を向いて願い事をしながら黙って食べるのが風習です。
- 神社参拝: 節分祭を行う神社で参拝し、健康と幸せを祈りましょう。
節分2025年に関するよくある質問
節分とは何ですか?
節分とは、立春の前日に行われる日本の伝統的な行事です。「季節を分ける」という意味があり、旧暦では立春が新年の始まりとされていたため、邪気を払い福を招く意味があります。
2025年の節分の日はいつですか?
- 2025年の節分の日は「2月2日(日曜日)」です。
なぜ2025年の節分の日が2月2日(日曜日)なのか?
節分の日は、立春の前日と定められています。地球の公転周期と暦のわずかなズレを調整するために毎年変動します。地球は約365.2422日で太陽の周りを一周するため、通年(365日)との誤差が生じます。 この誤差を補正するために閏年や立春の日付の見直しが行われ、その影響で節分が2月2日や2月4日になる年もあります。2025年は立春が2月3日(月曜日)にあたるため、その前日の2月2日が節分の日となります。
通常、節分は2月3日が一般的ですが、立春がずれることで節分の日付も調整されます。この現象は地球の公転周期と暦のずれにより起こります。2025年の節分が特定の日曜日に当たるのはこの調整が理由です。 次の2日の節分の日は2029年2月2日(金)となります。
節分の豆まきの由来は何ですか?
豆まきの風習は平安時代に遡り、邪気を追い払う「追儺(ついな)」という儀式に由来します。炒った豆を鬼に投げつけ、悪霊を退治し、福を呼び込むとされています。
恵方参りとは
恵方参り(えほうまいり)は、日本の古来から伝わる正月行事の一つで、 毎年の「恵方」と呼ばれる縁起の良い方向に向かって神社やお寺に参拝する風習を指します。 この「恵方」とは、歳徳神(としとくじん)という福を司る神様が在位するとされる方角で、十干に従って毎年変わります。
年初めに吉方(生気方・養者方)へ参詣する習慣は、11世紀初頭まで遡ることができます。 当時は歳徳神の方角に向かい厄を避け、運気を高めることが一般的な信仰とされていました。 江戸時代になると、この風習は庶民にも広がり、節分や立春と結びついて商売繁盛や家内安全を祈願する行事として定着しました。
特に関西地方では、節分に恵方参りが盛んに行われており、この風習の名残として現在の節分に「恵方巻」を食べる習慣が生まれました。 これは恵方に向かって願いを込めながら太巻きを食べることで福を呼び込む行為とされています。
恵方参りは、神社やお寺に参拝するだけでなく、自宅から恵方に向かって願い事をすることも含まれます。その年の福徳、健康、繁栄を願う行為として手軽に取り入れることができるのも特徴です。
2025年の恵方は西南西(西寄り)です。この方向に意識を向けて参拝や願い事を行うことで、一年の幸福や成功を祈ることができます。
恵方巻が全国的に広まった理由
恵方巻が全国的に広まった背景には、大手コンビニチェーンが節分の行事食として「恵方巻」を販売し始めたことが大きく影響しています。以下に、恵方巻の広まりに寄与した主な要因を挙げます。
- 1932年: 大阪鮓商組合が「恵方を向いて巻寿司を丸かぶりする」という風習を紹介するチラシを配布。
- 1970年代: 大阪の海苔業界が節分に「恵方巻」を広めるために積極的に宣伝活動を展開。
- 1989年: 広島県のセブンイレブンが節分の太巻きを「恵方巻」という名称で販売を開始。これがヒット商品となる。
- 全国展開: コンビニでのヒットを受けて、全国チェーンのスーパーや百貨店も節分時期に「恵方巻」の販売をスタート。
現在では、節分に恵方巻を食べる風習は全国的に定着し、多くの家庭で行われる行事となっています。
恵方巻きの定番の具材
恵方巻きは、節分に食べられる日本の伝統的な太巻き寿司です。その中には、縁起の良いとされる7種類の具材が詰められており、それぞれに意味が込められています。 以下は、恵方巻きに使用される代表的な具材です。
- 穴子やうなぎ: 長寿や活力を象徴する具材で、疲労回復にも効果的とされています。
- えび: 目玉が飛び出ていることから「めでたし」という語呂合わせ、ひげが長く腰が曲がっていることから「長寿」。長寿の象徴で、腰が曲がるまで元気でいることを願う意味が込められています。
- かんぴょう: 細長い見た目から「長寿祈願」。幸運を巻き込むという意味を持つ具材で、甘く煮た味が特徴です。
- しいたけ: 形が陣笠に似ていることから、「身を守る」。豊作や健康を象徴し、だしの旨味が味に深みを与えます。
- きゅうり: 「九の利」という語呂合わせから「9つの利益を得る」という意味。青々とした見た目が清涼感を与え、邪気を払うとされています。
- だし巻き卵: 黄色の色味から「金運上昇」の意味。家庭の団らんや和やかな生活を願う具材で、甘い味わいが特徴です。
- 桜でんぶ: 鯛などの白身魚から作られることから「めでたい」という意味。桜色が春の訪れを連想させ、見た目にも華やかな印象を与えます。
恵方巻きの具材は、それぞれの味わいが調和し、食べる人に幸運や繁栄をもたらすと信じられています。自宅で作る際には、これらの具材を取り入れることで伝統の味を楽しむことができます。
丸かぶり寿司・恵方巻の食べ方
- 恵方(今年の方角)を確認する: 毎年節分の日には、その年の「恵方(吉方位)」が設定されます。この方角を向いて恵方巻を食べる。
- 一気に食べる: 恵方巻は切らずにそのまま丸かぶりで食べる。
- 心の中で願いを唱え、無言で食べ切る: 途中で話したりするとご利益が逃げると言われているため、黙々と食べるのがポイントです。
節分が有名な寺社
節分の行事で有名な寺社には、日本全国で多くの注目スポットがあります。以下にその中でも特に有名な寺社をご紹介します。
関東地方
- 成田山新勝寺(千葉県): 日本で最も有名な節分会として知られており、毎年大相撲力士や芸能人が参加します。歌舞伎界とも縁が深く、市川團十郎さんが参加することもあります。
- 浅草寺(東京都): 江戸時代から節分行事が盛大に行われており、年男による豆まきや「福聚の舞」が披露されます。文化芸能人が参加する「文化芸能人節分会」も開催されます。
- 池上本門寺(東京都大田区): プロレスラー力道山のお墓があることで知られ、節分追儺式にはプロレスラーやアスリート、タレントが参加します。
- 赤坂日枝神社(東京都永田町): 江戸城の鎮守として徳川家に大切にされてきた神社で、クジ付きの豆まきが行われます。
関西地方
- 八坂神社(京都): 節分の日とその前日合わせて9回の豆まきが行われ、歌舞会の芸妓さんや舞妓さんによる舞踊奉納も見られます。
- 伏見稲荷大社(京都): 節分祭が盛大に行われます。
- 平安神宮(京都): 節分祭では、厄除けや福を招く儀式が行われます。
- 藤森神社(京都): 節分行事が行われ、地元の人々にも愛されています。
- 北野天満宮(京都): 節分行事が行われ、学問の神様への参拝者で賑わいます。
- 千本釈迦堂(大報恩寺 京都): おかめ福節分祭が開催され、特有の風情が感じられる行事です。
東北地方
- 中尊寺(岩手県): 天台宗の東北大本山であり、厄男と厄女による豆まきが行われます。
その他の有名な寺社
- 増上寺(東京都): 節分の特別行事が行われ、多くの参拝者が訪れます。
- 出雲大社(島根県): 節分行事で知られる神社の一つです。
- 大宰府天満宮(福岡県): 節分祭で多くの人が訪れます。
- 鶴岡八幡宮(神奈川県): 節分の豆まきや祈祷が行われます。
京都の「四方参り」
京都では、京都御所の四方の鬼門を護る伝統行事「四方参り」が有名です。「吉田神社」「八坂神社」「壬生寺」「北野天満宮」の四社を巡り、邪気を払う風習があります。
2025年の節分を楽しむためのヒント
節分をさらに楽しむために、家族や友人と一緒に豆まきをするだけでなく、オリジナルの恵方巻きを作るのもおすすめです。また、地域の神社で開催される節分祭に参加することで、伝統文化を深く体験できます。
恵方参り・方角のマップ
恵方参り・恵方の地図・マップアプリです。赤い点線が恵方の方向となります。方角を確認して神社、お寺などの仏閣をチェックしてください! 恵方参りをする神社、仏閣の探し方は、職場や住んでいる場所からの線の直線上、または近い場所を調べることができます。